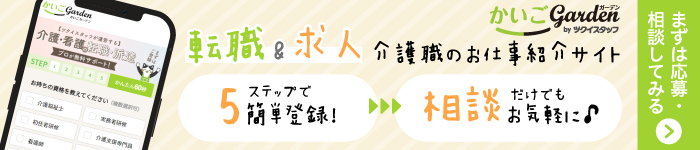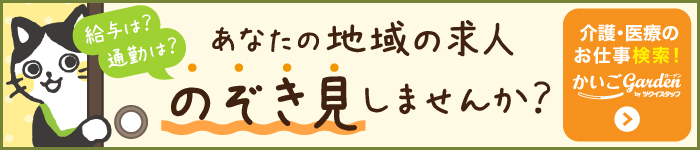介護の必要度が低い「要支援者」やそれ以外の高齢者に向けた事業、それが「介護予防・日常生活支援総合事業」、通称「総合事業」です。「地域包括ケアシステム」の構築に向け、2017年から各地方自治体で実施が始まっています。
介護の必要度が低い「要支援者」やそれ以外の高齢者に向けた事業、それが「介護予防・日常生活支援総合事業」、通称「総合事業」です。「地域包括ケアシステム」の構築に向け、2017年から各地方自治体で実施が始まっています。
今はまだ介護らしい介護は必要ないけれど、日常生活で困る場面や健康面で不安な部分もある・・・そんなお年寄りにぜひ役立てていただきたいのが、総合事業で提供される「介護予防ケアマネジメント」。ケアマネジメントではその人のニーズに合った「ケアプラン」を作成していきます。
要介護状態になることをさまざまな面から防ぎ、住み慣れた地域でできるだけ長く元気に過ごしてもらうのが総合事業のねらい。今回は一連の流れやケアプランの詳細にスポットを当ててご紹介していきましょう。
総合事業の仕組み

総合事業は「要支援1・2」認定を受けた人か「基本チェックリスト」で該当した人を対象とする「介護予防・生活支援サービス事業」と、すべての高齢者が利用できる「一般介護予防事業」の2種類に分かれています。前者を利用する際には介護予防ケアマネジメントを行い、ケアプランを作成してそれに従って利用します。
【基本チェックリストとは】
65才以上の高齢者に向けた、心身の機能で衰えているところがないかをチェックするためのリスト。25個の質問に答えることで介護リスクを把握できる。
介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス(掃除・洗濯など日常生活上の支援)
・通所型サービス(機能訓練や集いの場などの提供)
・生活支援サービス(配食や見守り等)
・介護予防ケアマネジメント(上記のサービス等が適切に提供できるようケアマネジメント)
一般介護予防事業
・介護予防把握事業(閉じこもりなど問題を抱えた人を把握し、支援へつなげる)
・介護予防普及啓発事業(介護予防の普及・啓発を行う)
・地域介護予防活動支援事業(住民主体の介護予防活動のサポート)
・一般介護予防事業評価事業(目標達成状況などを検証、事業の評価を行う)
・地域リハビリテーション活動支援事業(リハビリ専門職による助言等) etc・・・
介護予防・生活支援サービス事業の利用の流れ
- 住所地の地域包括支援センターの窓口に相談する
- 「基本チェックリスト」で心身の機能についてチェックを行う
- チェックの結果、介護予防・生活支援サービス事業対象者となった方は、介護予防ケアマネジメント依頼書を提出し、名簿登録・被保険者証を発行してもらう
- 介護予防ケアマネジメントの実施
- ケアプランの交付
- サービス事業利用
- モニタリング・評価
介護予防ケアマネジメントとは

介護予防・生活支援サービス事業を利用するにあたって必要となる「介護予防ケアマネジメント」。これには「原則的な介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)」、「簡略化した介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントB)」、「初回のみの介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントC)」の3つの種類があります。本人の状態や周囲の状況などを鑑みてA、B、Cのどのタイプにするかを決定します。
ケアマネジメントA
アセスメント⇒ケアプラン案作成⇒サービス担当者会議⇒利用者へ説明し同意を得る⇒ケアプランの確定⇒サービスの利用を開始⇒3ヵ月に1回程度のモニタリング
ケアマネジメントB
アセスメント⇒ケアプラン案作成⇒利用者へ説明し同意を得る⇒ケアプランの確定⇒サービスの利用を開始⇒6ヵ月に1回程度評価を行う
ケアマネジメントC
アセスメント⇒ケアマネジメント結果を作成し利用者に説明し承諾を得る⇒サービス提供者に連絡⇒サービスの利用を開始
介護予防ケアマネジメントの実施やケアプランの作成は、住所地の地域包括支援センターに配置されているケアマネジャー、保健師、社会福祉士といった資格を持った職員が協働して行います。
介護予防ケアプランとは

介護予防ケアマネジメントでは、まず利用者や家族から詳細な聞き取りや評価(アセスメント)を行います。その次に、聞き取った内容から「介護予防ケアプラン(介護予防サービス・支援計画表)」の原案を作成。タイプAならサービス担当者会議にかけてから、BやCならそのまま利用者に内容を説明し、承諾を得たらケアプランの完成です。
「介護予防サービス・支援計画表」の様式は利用者氏名から同意のサイン欄まで30項目ほどに分かれており、これを埋めていくことで利用者の希望や目標、課題や方針など、必要な情報がもれなく記載できるようになっています。重要項目を一部ピックアップしてご紹介していきましょう。
目標とする生活
利用者に聞くだけでは漠然としていて具体的なイメージができないことも多いため、プラン作成者は利用者とともに生きがいや楽しみを話し合い、じっくり考えることが必要。あくまでも介護予防支援や本人の取組みで達成できる、具体的な目標でなくてはならない。利用者が介護予防に主体的に取り組むモチベーションになる部分なので、とても重要な項目となる。
アセスメント領域と現在の状況
「運動・移動について」「日常生活(家庭生活)について」「社会参加、対人関係・コミュニケーションについて」「健康管理について」の4つの領域ごとに状況を記載。本人と家族の両方から話を聞きつつ、また実際に作成者が観察した状況、主治医の意見書なども加味して記入する。
本人・家族の意欲・意向
利用者・家族の認識・意向を、具体的に 「○○できるようになりたい 」「手伝ってもらえば○○したい 」 などと記載。利用者と家族の意向が異なっていれば、それぞれ記載する。
領域における課題(背景・原因 )
各アセスメント領域における課題の背景や原因を、これまでの項目に記載した内容や、面談中の様子、その他の情報をもとに整理して分析する。現在だけでなく将来起こることが予測される課題も含め、その領域に課題があると考えられる場合は「□ 有」にチェックを入れる。
総合的課題
各領域における課題に共通する背景等を見つけ出し、優先度の高い課題順に1から番号をふる。
課題に対する目標と具体策の提案
評価可能で具体的な目標を記載する。具体策については介護保険サービス等だけでなく、セルフケアや家族の支援、老人会など地域活動の活用も盛り込むなど、さまざまな角度から利用者にとって最も適切と考えられるものを提案する。ここに記載する「目標」は、本人や家族の意向に左右されたものではなく、アセスメントに基づいた専門的な視点からの提案となる。
具体策についての意向 本人・家族
プラン作成者の提案に対する、本人や家族の意向を確認する。合意が得られた場合は「○○が必要だと思う」「○○を行いたい」等と記載。合意が得られなかった場合には、その理由となる本人や家族の考えを記載。
目標
前項目の本人・家族の意向を踏まえ、プラン作成者と利用者・家族が合意した目標を記載する。
目標についての支援のポイント
合意した目標を達成するための支援のポイント(安全管理上の問題やインフォーマルサービスの役割分担など)を記入する。
本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス
「誰が」「何を」するのかを具体的に記載する。
「介護保険サービスまたは地域支援事業 」
予防給付、地域支援事業のサービスの内容を記載し、どちらのサービス・事業を利用するかわかるように○印で囲む。
介護予防サービス・支援計画書の様式(厚生労働省ホームページ)
人の力を借りて上手に介護予防を

家族に迷惑をかけることなく、自分の力で元気に暮らしていきたい――そんな気持ちから自分なりに健康づくりをがんばっている高齢者の方はたくさんいらっしゃいます。でも、「今までのやり方がうまくいかない」「困ったな」と思ったら、積極的に人の手を借りてみるのも良いのではないでしょうか。お住まいの地域の地域包括支援センターで相談すれば、基本チェックリストで自分の介護リスクがよく分かります。
もし総合事業の対象者であることが分かれば、ケアマネジャーなどの資格を持ったプロが自分の課題を分析してくれて、最適なケアプランを作ってくれます。経験豊富な担当者はたくさんの引き出しを持っているので、自分では気づけなかった問題点や、目からウロコの解決策をどんどん出してくれるかもしれません。これからもずっと介護要らずで暮らし続けるために、ぜひ活用してみてくださいね。